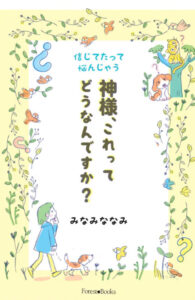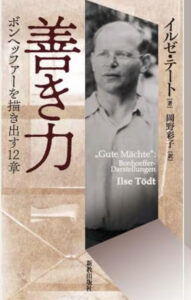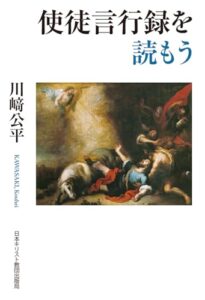
単に「働き」と呼ばれていたとも言われる新約聖書の「使徒の働き」。
『使徒言行録を読もう』(川﨑公平著、日本キリスト教団出版局、2千750円税込、四六版)の著者は「『教会の働き』と呼びたい」と言う。教会の祈祷会で語られた平易な語り口。教会の言葉は、「こと」(出来事)を含み、説教も、「人の存在と言葉が一つ」となるという指摘はAI時代に示唆的だ。ペテロの姿を例に「人を分け隔てなさらない神の思い」を知り、伝道者自身の悔い改めと成熟を促す。
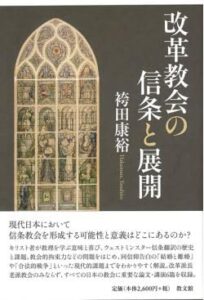 『改革教会の信条と展開』(袴田康裕著、教文館、2千860円税込、四六判)
『改革教会の信条と展開』(袴田康裕著、教文館、2千860円税込、四六判)は、日本キリスト改革派教会の信仰基準として採用されたウェストミンスター信仰規準をめぐる課題を中心に論じる。信条の拘束力をどうとらえるかという問題で、「本質」論、「全命題」論、「体系」論などそれぞれに注意を払う。結婚と離婚、合法的な戦争のテーマについても考察。「カテキズム、教理問答は、魂の対話相手」と勧める。
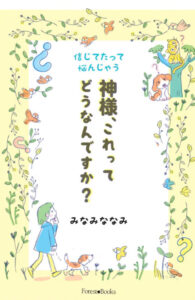
答えの出しづらい問題を、ユーモアあるマンガで、対話的に提示する
『信じてたって悩んじゃう 神様、これってどうなんですか?』(みなみななみ著、いのちのことば社 、千430円税込、B5判)。中絶、臓器移植、障がい、同性愛、宗教二世、イエスラエル・パレスチナ、戦中の教会などの問題を、結論ありきで語らない。ジレンマについて自問したり、編集者と語り合い、専門家や当事者に聞き取りもして丁寧に表現。

ナチスに抵抗したドイツの詩人、思想家のシュナイダーを解説する
『苦悩への畏敬 ラインホルト・シュナイダーと共に』(下村喜八著、ヨベル、千870円税込、四六判)。神の国、地の国の戦いは「まず一人の人間の心の中で起」こるという。「信仰」と「不断の祈りからくる活動」はボンヘッファーと比較される。
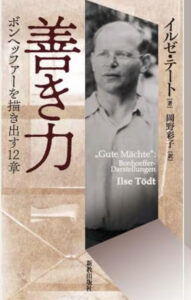
ボンヘッファー全集を手掛けた著者による講演集
『善き力 ボンヘッファーを描き出す12章』(イルゼ・テート著、岡野彩子訳、新教出版社、3千960円税込、四六判)はボンヘッファーの生涯の流れに沿って再編された。平和論の章は、来日講演から。西洋と日本の戦争を比較する。「倫理はただ『純粋に検討して』語ることができるだけではなく、『具体的な判断と決断を下す冒険が必要とされる』」という著者の要約は、人知を超えた神の平和を求める「抵抗」への言葉となる。
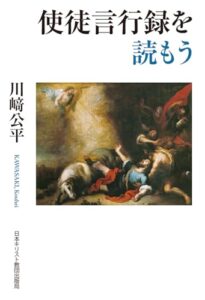
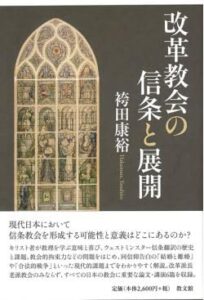 『改革教会の信条と展開』(袴田康裕著、教文館、2千860円税込、四六判)は、日本キリスト改革派教会の信仰基準として採用されたウェストミンスター信仰規準をめぐる課題を中心に論じる。信条の拘束力をどうとらえるかという問題で、「本質」論、「全命題」論、「体系」論などそれぞれに注意を払う。結婚と離婚、合法的な戦争のテーマについても考察。「カテキズム、教理問答は、魂の対話相手」と勧める。
『改革教会の信条と展開』(袴田康裕著、教文館、2千860円税込、四六判)は、日本キリスト改革派教会の信仰基準として採用されたウェストミンスター信仰規準をめぐる課題を中心に論じる。信条の拘束力をどうとらえるかという問題で、「本質」論、「全命題」論、「体系」論などそれぞれに注意を払う。結婚と離婚、合法的な戦争のテーマについても考察。「カテキズム、教理問答は、魂の対話相手」と勧める。
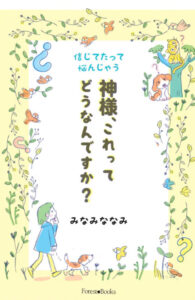

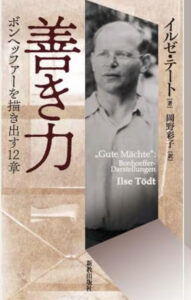
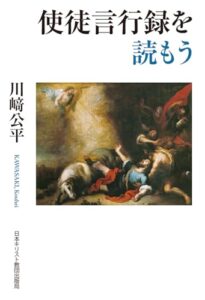
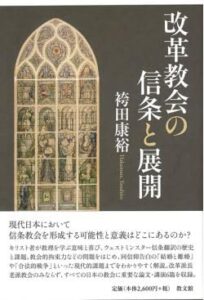 『改革教会の信条と展開』(袴田康裕著、教文館、2千860円税込、四六判)は、日本キリスト改革派教会の信仰基準として採用されたウェストミンスター信仰規準をめぐる課題を中心に論じる。信条の拘束力をどうとらえるかという問題で、「本質」論、「全命題」論、「体系」論などそれぞれに注意を払う。結婚と離婚、合法的な戦争のテーマについても考察。「カテキズム、教理問答は、魂の対話相手」と勧める。
『改革教会の信条と展開』(袴田康裕著、教文館、2千860円税込、四六判)は、日本キリスト改革派教会の信仰基準として採用されたウェストミンスター信仰規準をめぐる課題を中心に論じる。信条の拘束力をどうとらえるかという問題で、「本質」論、「全命題」論、「体系」論などそれぞれに注意を払う。結婚と離婚、合法的な戦争のテーマについても考察。「カテキズム、教理問答は、魂の対話相手」と勧める。