〝アート〟は共感の「方法」になる 立教大学と森美術館で共同トークセッション開催
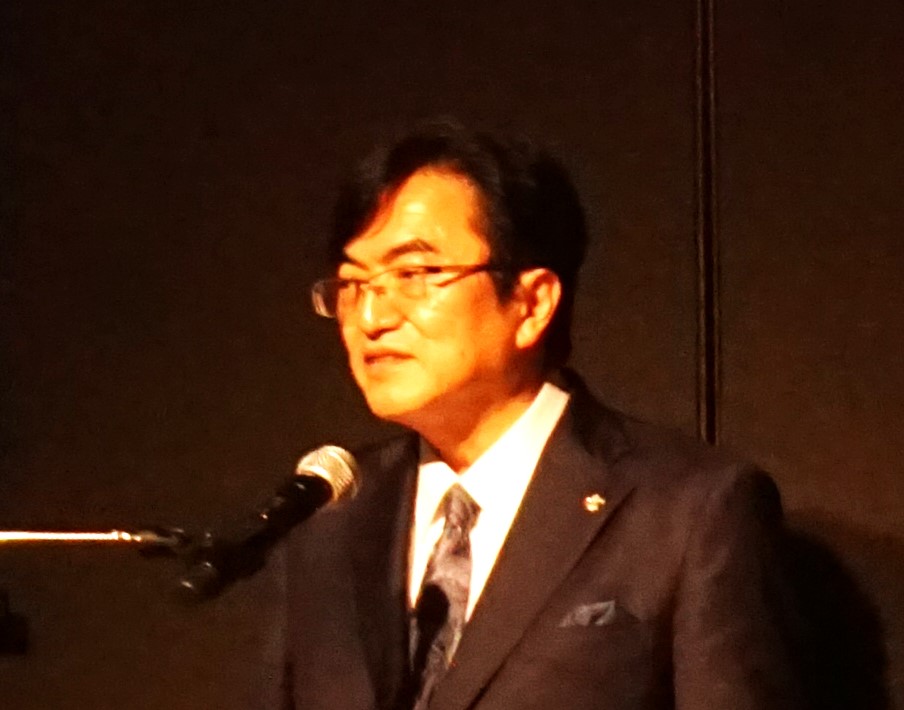
西原氏
「アート」が、世界の見方にかかわることが議論された。立教大学と森美術館の共同プロジェクト、トークセッション・シリーズ「知らない世界とつながってみる」が6月16~18日に東京・港区の六本木ヒルズで開かれた。同美術館の展示「ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会」(9月24日まで)の関連企画だ。同大学の教授たちと、キュレーター、アーティストらが対話した。
同大学総長の西原廉太氏(同文学部キリスト教学科教授)と、同美術館館長の片岡真実氏は、30年来の親交があり、今回の企画につながった。昨年は、国際芸術祭「あいち」の芸術監督を務めた片岡氏や関係者を招いたシンポジウムを立教大学のチャペルで開いた。今回は学校法人立教学院の中・高・大生が本展の音声解説を作成するワークショップも行った。

片岡氏と加藤氏
全体で貫かれていたのは、「アート」(Art)を「美術」という一科目にとどめず、あらゆる領域にかかわる「方法」としてとらえる視点だ。これはキリスト教学校などを中心に日本でも導入されてきた「リベラル・アーツ」(Liberal Arts)に通じる。リベラル・アーツは多分野を総合的に学ぶ教養として近年注目されるが、西洋の修道院や大学の基礎教育となった「自由七科」にさかのぼれる。
西原氏は「第一の書物」として言葉で書かれた「聖書」、「第二の書物」としての「自然」を説明。自由七科はこれらに対応していることを示した。「文系理系関係なく学んだ。これらを基礎に、大学は、魂、人間、社会の痛みそれぞれの『聖職者』(司祭、医者、法律家)を養成した」と言う。リベラル・アーツの本来的な意味として、「他者の痛みに共感し共苦する感性を育てること」などを挙げた。
美術史が専門の加藤磨珠枝氏(立教大学文学部キリスト教学科教授)もリベラル・アーツや「美術」という語の由来に触れ、「アートは東洋の『藝』(芸)に近く、人と世界のかかわりを理解する総合知を導く」と述べた。
片岡氏は、冷戦以後の多元化した世界を現代アートが反映していることを示した上で、「現代アートは分からないと言われる。しかし背景や文脈を知り、作品を見直すと理解が深まる。現代アートは世界を学ぶ教室になる」と語った。「展示室を歩けば、『国語』や『社会』では世界の多様性を学ぶ。『算数』や『理科』では世界の真理探究の営みを知る。各分野を掘り下げていくと、他の分野とつながっていることが分かる」と勧めた。
トークセッションは、文学、宇宙物理学、社会学、考古学、文化人類学、美術史の各分野で展開した。議論となったのは、言語と非言語、情報を分かりやすく伝える「ナラティブ」(物語)の可能性と危険性、定義からはみ出る「ノイズ」(雑音)の扱い、などだった。これらは脱中心主義、脱植民地主義、ポストモダニズムなどの議論ともつながる。これらの理解や対話には、西原氏が勧めた「物語を手仕事的に子どもたちに伝え、子どもたちの一つひとつの物語に丁寧に耳を傾け、子どもたちを『知らない世界』へとつなげる」という教育姿勢がヒントになりそうだ。【高橋良知】
(2023年07月23日号 04面掲載記事)
