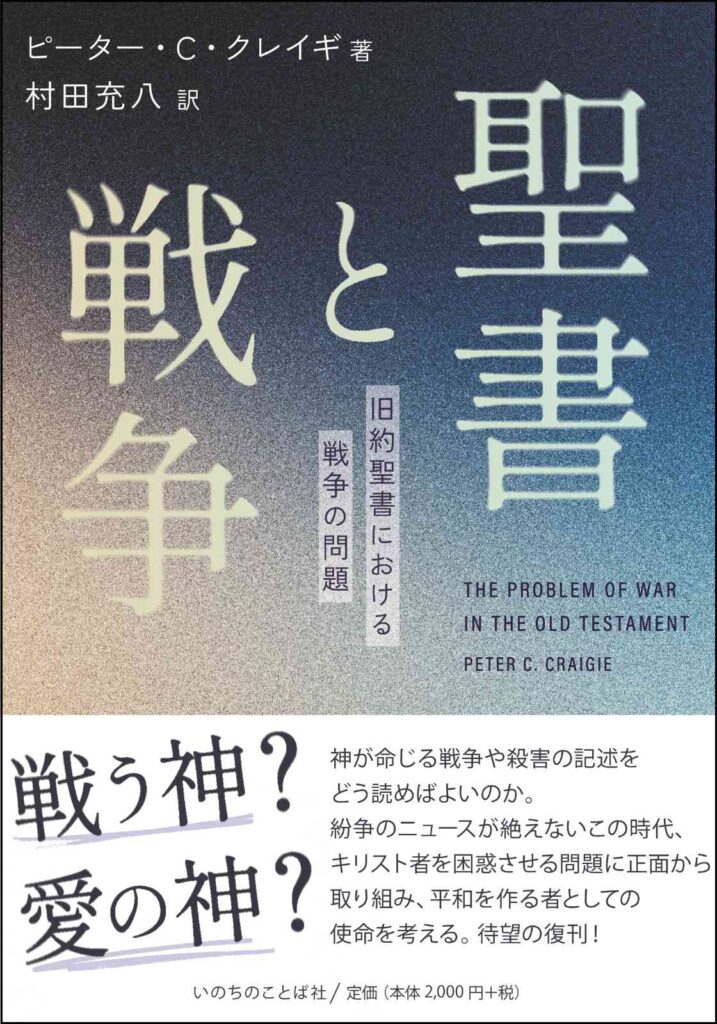本書は、英語の原書が1978年に出版され、日本語訳は90年に出版、その後2回の増刷の後に3回目の改訂版、そして今回さらなる改訂版として復刊されたものである。原書の出版から45年以上が経つが、良い本は繰り返し読まれるということだろう。同時に、この著書が読み継がれているということは、45年前も、今も、この世界は戦争に包まれており、キリスト者にとって戦争とどのように向き合えば良いのかは変わらぬ課題であるということだ。
著者は、一切の戦争に反対する立場の非戦論者でもなく、正義による戦争を正当化する立場でもない。著者の戦争に対する視点は、ある意味では非常に現実的である。著者にとって戦争とは、「神が、罪ある人間存在を用い…人間の歴史に参与」(67頁)されることである。また、人間は罪深さから逃れることはできず、故に、国と国との戦争もまた人間の歴史においては避けることのできない「必然性の秩序としての暴力」(189頁)であるという。それではキリスト者は、戦争を「必然的」なこととしてただ傍観するしかないのか。
著者はその一つの説明として、聖書のたとえ話を取り上げる。たとえば、新約聖書に記される善いサマリア人のたとえは、レビ人たちが瀕死(ひんし)の旅人のそばを通り過ぎるところまでだけを切り取って読んでも、そのたとえ話の真意を理解することはできない。サマリア人の最後の行為まで読んで初めて、このたとえ話が示そうとしている善き隣人としてのあり方を理解することができる。
これまでの歴史の中で、聖書の戦争の記述だけが切り取られた結果、戦争の正当化の理由づけとして聖書が用いられることも多々あった。しかし、先のサマリア人のたとえと同様に、旧約聖書に記される戦争の記述は、それだけを切り取っては、神の歴史におけるその意味を理解することはできない。聖書全体の中でその記述が読まれるときに見出されることは、戦争の中にある人間の罪深さ、敗北、そしてその中から出てくる悔い改めと希望、さらに、最終的ゴールつまり終末論的ビジョンの到達点としての神の平和の完成である、というのが著者の主張である。
本書のタイトルは『聖書と戦争』だが、本書を通じて著者が繰り返し示していることは、戦争のその先にある平和の希望である。「はじめに」の中で、本書は教育に携わる方々に向けに執筆された、と述べられている。次の世代に平和を受け渡すこと、それが著者と本書を手に取る読者が最終的に目指す地点ではないだろうか。
(評・岩田三枝子=東京基督教大学副学長、神学部部長)
(2024年08月11日号 05面掲載記事)