4月18日号紙面:なぜ西洋キリスト教は“衰退”したか テイラー著『世俗の時代』めぐってICUでシンポ開催
なぜ西洋キリスト教は“衰退”したか テイラー著『世俗の時代』めぐってICUでシンポ開催
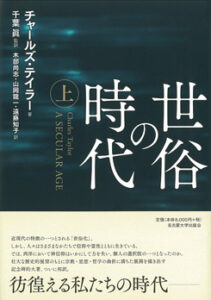
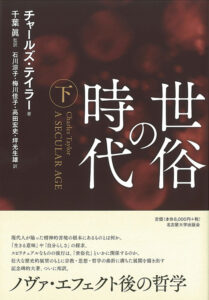
『世俗の時代』上下、チャールズ・テイラー著、千葉眞監訳、 木部尚志・山岡龍一・遠藤知子・石川 涼子・梅川 佳子・高田 宏史・坪光生雄訳、名古屋大学出版会、各8千800円税込
かつてのキリスト教中心地、西欧は今や「宣教地」と言われることもあるほど、キリスト教の勢力が衰退したかのように見える。西欧は多様な思想・制度改革が試みられ、いち早く「世俗化」が進んだ地でもある。ただその内実は単純ではない。昨年翻訳出版された、チャールズ・テイラー著『世俗の時代』(千葉眞監訳、名古屋大学出版会)では、キリスト教国の近代化・世俗化という複雑なプロセスが思想的に考察された。この出版記念集会では、非西洋諸国も含めた様々な近代化・世俗化の在り方についても問いかけられた。【高橋良知】
「改革」から「排他的 人間主義」拡大まで
同書著者のチャールズ・テイラー(1931~)は政治哲学者と称されるが、扱う領域は、西洋哲学史、政治思想史、言語哲学、現象学、美学論、文学論と多岐にわたる。近年「新しい実在論」で注目される哲学者マルクス・ガブリエルの議論にも参加(『新実存主義』岩波新書、2020)し、抽象度の高い最先端の哲学にも業績がある。
『世俗の時代』原著は2007年刊行。邦訳でも上下巻計900頁を超す。出発点の問題意識は「西洋社会において、例えば一五〇〇年の時点では神を信じないことは実際に不可能だったのに、二〇〇〇年には多くの人にとって、信仰をもたないことが容易であるだけでなく不可避なことにすら思えるようになったのは、いったいなぜなのか」(上巻30頁)だ。
世俗化については、公共的空間の世俗化(世俗性1)、宗教的信条と実践の衰退(世俗性2)、宗教が様々な選択肢の中の一つとなる(世俗性3)の3点を挙げ、特に世俗性3に注目した。
歴史的考察では、著者がいわゆる宗教改革を含む「大文字の改革」があったとする中世後期から始まる。17、18世紀の啓蒙(けいもう)時代を経て、キリスト教の超越的次元を全面的に拒否する「排他的人間主義」が広がる19~20世紀前半(動員の時代)、「信仰の内面化・個人化・多様化」が進み、スピリチュアルな関心が高まる1960年代以降までの歴史を論述する。
さらに世俗性3の考察を深め、超越を拒否する「閉鎖型」の「内在的枠組み」、信仰と不信仰の「交差的圧力」の作用、「超越への欲求と日常の人間的欲求のディレンマ」、「暴力と非暴力のディレンマ」などを指摘した。
考察対象は北大西洋地域に限定され、テイラーがベースにするカトリックの比重は高いが、プロテスタントと並行して論じられ、仏教との比較もある。中世、啓蒙時代、現代の哲学者の思想のほか、文学者への言及も多い。
宗教と啓蒙主義が複雑に協働

国際基督教大学(ICU)キリスト教と文化研究所は「シンポジウム:近代とキリスト教 チャールズ・テイラー『世俗の時代』(名古屋大学出版会)」を2月20日にオンラインで開催した。監訳した千葉眞氏(ICU名誉教授)が「近代西洋の光と影-テイラーの世俗化論から見えてくるもの-」と題して講演した。
「事態は単線的ではなく、より複雑だ。中世後期に『大文字の改革』があり、プロテスタンティズム、それに触発されたカトリシズムの『対抗宗教改革』、これらに連動して啓蒙主義が協働した。宗教的な改革と社会的・政治的な改革とは手を携えて進行していた」として、テイラーの世俗化論を「複合的世俗化論」と名付けた。
「ラテン系キリスト教のいくつかの教説や教義、慣習や実践の『偏向』が結局人々をキリスト教と教会から離脱させ、排他的人間主義の側に追いやった」という側面も指摘した。
その中で、宗教の貢献として、「よきサマリア人」や「放蕩息子」のたとえに現れるアガペー(無償の愛)を挙げた。この愛と赦しが宗教的暴力を乗り越えるとした。
「テイラーは宗教と啓蒙主義双方の危険性を鋭く指摘した。宗教については原点からの逸脱、堕落、腐敗、悪用、原理主義化を、啓蒙主義については人間理性の傲慢と自己絶対化 代替宗教への堕落を批判した」
世俗化について、哲学者のリチャード・ローティ、ジョン・ロールズ、ユルゲン・ハバーマスとも対比した。ローティは「すべての宗教的言説を公共的理性の領域からしめだすべき」とした。ロールズは「公共的」の担い手を市民、統治の当事者、統治三部門(立法部、行政部、司法部)に限定しつつ、奴隷制廃止運動や公民権運動での宗教的言説を評価した。ハバーマスは宗教的言説を世俗的言語に翻訳することで公共圏の多様性を確保しようとした。
テイラーは、ロールズ、ハバーマスの「憲法的・制度的アプローチ」を評価しつつ、宗教に融和的な世俗主義(自由、平等、すべての信仰共同体の意見表明と参加の保障、諸宗教間の調和と礼節)を擁護する「倫理的アプローチ」を主張した。
千葉氏の講演を受けて、山岡龍一(放送大学教授)、高田宏史(岡山大学准教授)、木部尚志(ICU教授)の各氏が応答した。本書の叙述の仕方、世界各地で起きているポピュリズム、宗教右派の問題、西洋中心主義と植民地や北大西洋以外の地域との相互影響関係、世俗と宗教の境界線、本書で言及のないティリッヒ、ハルナック、バルトやボンヘッファーなどのプロテスタント神学との比較、普遍的な道徳の源泉を日本でどう見出すか、などの課題が上がった。
非西洋圏からのテイラーへの応答は“A Secular Age beyond the West” Cambridge University Press,2019としてまとめられ出版されている。
人類の中心主題の中に存在
「近代英国哲学におけるキリスト教神学の影響」

本講演の背景には、ICUキリスト教と文化研究所が中心になり、進めている研究プロジェクト「近代英国哲学におけるキリスト教神学の影響」がある。
同研究所所長の矢嶋直規氏は、「西欧諸国の、一見無関係と思える哲学にもキリスト教との応答関係がある。明確にキリスト教を中心主題にすえているデカルトやライプニッツといった大陸系の哲学に比べ、英国の経験論は世俗的と見られがち。だが本質はキリスト教との対立ではない。どのように新しい時代にキリスト教を適応しようとしたかが焦点となってきた」と話す。
啓蒙主義の時代、理神論や無神論に対して伝統的な信仰をどう守り抜くかという問題があった。「この時代を代表する哲学者ジョン・ロック(1632~1704)も、当初キリスト教擁護のつもりで、啓示を含めた信仰と理性の両立を図った。だがその後、その思想は理神論に利用されてしまった経緯があります」
無神論者と見なされることもある哲学者デイビッド・ヒューム(1711~76)についても、「生涯にわたって信仰、宗教の問題を考えていた。『真の宗教とは何か』という問いは、『真の哲学とは何か』と同じ問題意識だった。無神論とは違う」と言う。「ヒュームの懐疑主義は、理性が本当に真理を示すことができるかへの懐疑だった。宗教戦争やテロリズムの根本的な原因は理性。宗教自体が健全になるためにも、自分だけが正しいと相手に押し付けるのではなく、誠実な理性で対処することが必要。それは宗教的な人だけではなく、どうやって異なる意見を持つ人たちとよりよく生きるかという近代哲学の問題につながります」
「人間とは何か、どうやって他者と生きるかという問いは、神の前に立つ人間としての生き方を考えてきたキリスト教が成立時点からもっていた問いだ。キリスト教の影響は現代では小さいと思われるかもしれないが、西洋文明、人類の中心問題であり続けていることを改めて考えていただければ」と勧めた。
