
依存症の回復のプログラムとして知られる「12ステップ」。それを霊的成長のために再構成したプログラムを『語らいと祈り 信仰の12ステップに取り組んだ人々の物語』(松下景子著、ヨベル、千650円税込、四六判)は紹介する。家族依存、うつ、怒り、などを抱えた人々の回復の事例を匿名で語る。安心できる場での「言いっぱなし」「聞きっぱなし」からやがて心の解放のステップが踏まれる。著者自身が「教職者夫人」として抱えた葛藤を明かし、牧師、牧師夫人にこの働きを勧める。同書は2024年第10回おふぃす・ふじかけ賞受賞。
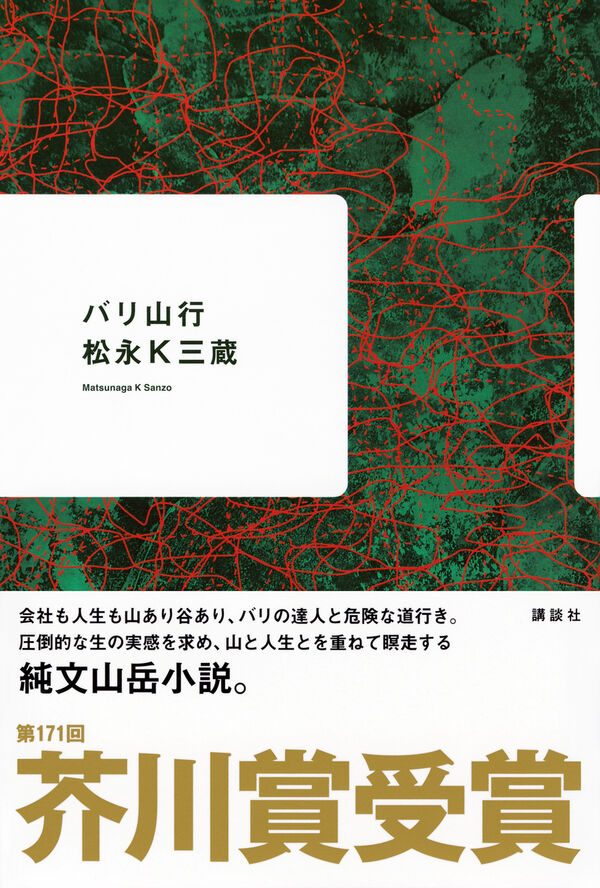
「…登山っていうのはちゃんと整備された道を、ある意味では歩かされているんですよ…」。
2024年夏の芥川賞受賞作『バリ山行』(松永K三蔵著、講談社、千760円税込、四六判)の書名の由来は「バリエーション山行」。「通常の登山道でない道」を行くことだ。本書では、とある会社の登山サークルを描き、山と社内を対比する。徐々に社内の人間模様が明らかになり、社の「経営方針転換」により不穏な影が差す。
一方主人公は社内の達人と草をかき分け「バリ山行」にのめり込む。そこで体験するものは、「本物の危機」だが、身体的なものだけでなく、超越的な様相を帯びている。著者によるエッセイ(『文学界』8月号、文藝春秋)を合わせて読むと、本書の底流にあるものが分かるかもしれない。
一つ言えるのはダンテ『神曲』の地獄巡りとの関連だ。文学は「問い」以上のものを示すべきだという信念もかいま見える。もう一つ分かることは、思春期の著者の激しい喪失と悲嘆(グリーフ)に寄り添ったクリスチャンの友人の存在があった、ということだ。
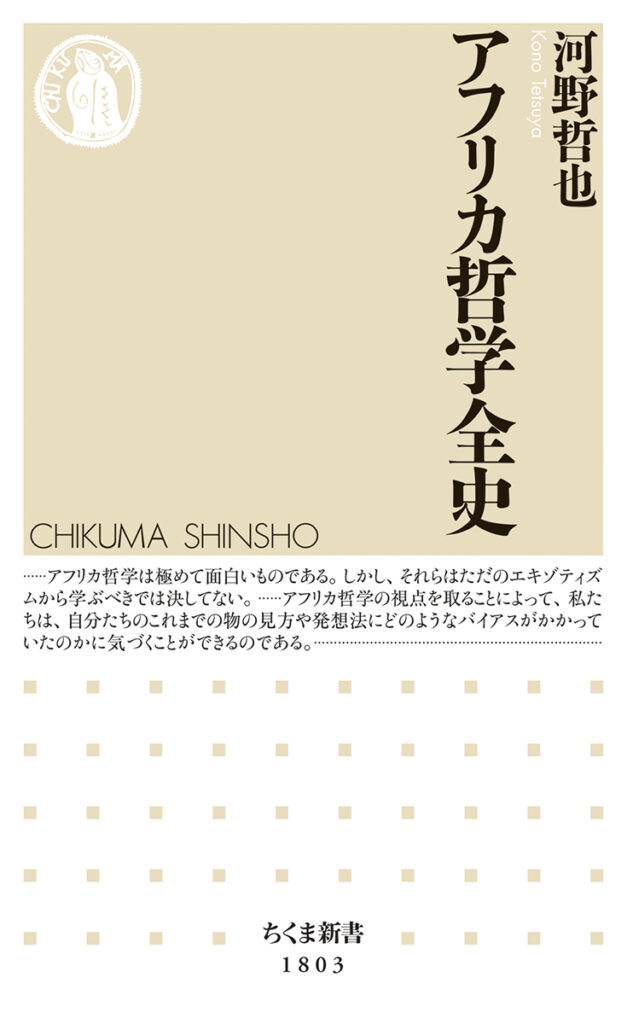
急激な人口・経済成長もあり、従来の「アフリカ観」が見直されている。キリスト教においても、アウグスティヌスなど主要な古代教父の多くはアフリカ系だった。『アフリカ哲学全史』(河野哲也著、筑摩書房、千430円税込、新書判)は、「前植民地時代」と「現代」によって、植民地時代の「西洋哲学」を挟み込んで解体する。「西洋哲学」のルーツとしてのアフリカ、「西洋哲学」の枠外のアフリカを明らかにした。現代においては倫理学、和解の哲学のほか、アフリカ独自の言語哲学、認識論、心身論、共同体論を紹介。著者は西洋と東洋の対立をこえて、アフリカの視点を加えた「知の三点測量」によって「世界哲学」を構想する。
