[レビュー3]キリスト教とは『宗教改革の知的な諸起源』『キリスト教 本質と歴史』『近代日本のキリスト者』
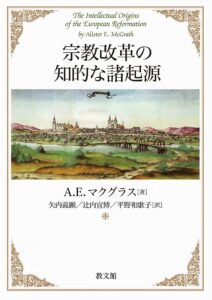
ルター派と改革派の分岐点は、「宗教改革」以前にさかのぼれる。『宗教改革の知的な諸起源』(A・E・マクグラス著、矢内義顕・辻内宣博・平野和歌子訳、教文館,5千280円税込、A5判)は多元的なキリスト教の姿を描いた。中世からの別々のルーツをもつ「小宗教改革」が続出し、それらの相互作用で「大宗教改革」となるという見方は、「大文字の宗教改革」(テイラー『世俗の時代』)とつながる。
第一部でルネサンスの人文主義と後期中世のスコラ学諸思想について、第二部では聖書解釈学、教父の証言について、それぞれルター派、改革派の起源を探る。それら「小改革」は地域性を持ち、諸学派との人的交流、文通、出版を通して形成された。
同書の言う「知的」とは、社会主義的な歴史観ではなく、思想そのものの系譜を強調すること。
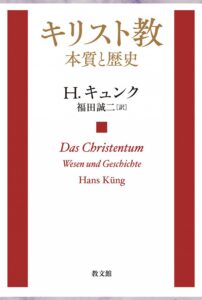
キリスト教は他宗教や世俗の思想と何が違うか。『キリスト教 本質と歴史』(H・キュンク著、福田誠二訳、教文館、9千680円税込、A5判)はその根源を問う。著者はカトリック信仰に立ちながら体制批判をし続けた。宗教間平和活動に積極的で、排他的ではない「キリスト中心主義」を重視する。
冒頭で「本質」を確認した後、原始キリスト教、古代、中世、宗教改革、近代のパラダイム転換を考察する。特にローマ・カトリックのヒエラルキー化、中央集権化のプロセスを明らかにし、同様のプロセスをプロテスタント教会にも見出す。各時代、体制ごとに女性の在り方を指摘するのも特徴だ。著者は今年4月に召天した。日本語版の序文では、文化、倫理、信仰の「二重国籍問題」を投げかける。

日本の近代化を重視すれば、個々のキリスト者の在り方が観念化され、「戦争協力」「天皇制」の批判だけではともすれば外在的な批判に陥る。それらの課題を乗り越えるために、『近代日本のキリスト者―その歴史的位相』(村松晋著、聖学院大学出版会、4千950円税込、A5判)は、代表的なキリスト者の内在的な思想展開を読み解いていく。
第一部では天皇をめぐる「熱情」について、柏木義円、住谷天来、南原繁を、第二部では川西実三、二瓶要蔵、住谷、深津文雄、第三部では「日本的基督教」をめぐり、南原、関根正雄、量義治を取り上げる。
深津は元売春女性保護にかかわり、保護施設「かにた婦人の村」を創立した。「底辺」よりもさらに「底」の「底点」を強調し、「共産党入党宣言」を出した赤岩栄牧師に共感しつつも、共産主義とは一線を画した。
著者は「日本的なキリスト教」に関心を向けるが、安易な日本文化肯定論については警戒する。
